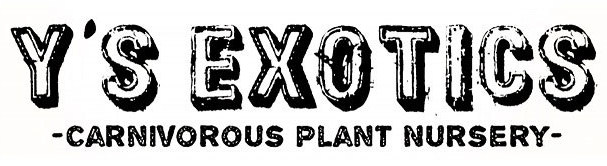環 境
1.日照
植物の成長には光合成によって炭水化物を作らせることが重要です。日本での太陽光は、夏の晴天で(10万ルクス)、冬の晴天(5万ルクス)あります。ほとんどのネペンテスは5万ルクス以下の光線量でうまく育つようで、夏の日中の直射にたいしてはダイオネットなどで50%~80%位の遮光する必要があります。これはあくまでも栽培するにあたっての目安で、温度・通気・湿度
または栽培する種類、それまでの環境、根の状態などで変わってきます。ネペンテスは日照に対して適応性があり徐々に馴らすと、健全な株なら相当な強光にも耐えられるようになります。気温45℃遮光30%のような環境にも耐えることができるようになる種類もあります。
ネペンテスが袋をつけなくなる一番の原因は、光線不足でしょう。植物は、光線を光合成で糖分などのエネルギー物質に変え、そのエネルギーを使って成長するのですから、光量が不足すると生育が鈍ります。ネペンテスは比較的強い光線を好む植物ですので、弱光線を好むネペンテスでも、まったくの日陰においては大きな袋をつけないでしょう。最良の光線は、高温をともわない東からの日光、または適当な遮光をした南からの日光で、葉焼けしないぎりぎりの光線にあてるのが理想的です。しかしながら日焼けギリギリの高カロリー栽培をするとなると各品種の特性をよく理解し、また細かな管理を必要とするので多くの栽培家は遮光を強くして栽培します。
ネペンテスは受ける光線量に順応しようとして葉や袋が色々な変化を示すので、適当な光線があたっているかは、ネペンテス自体を観察することによってわかります。一般に、健康なネペンテスの葉は明るい緑色(芝生色)に見えます。これは、虹と同じ色を含む目に見える光線のうち、緑の光以外を葉が吸収して光合成などに使い、使わない緑の光が反射されて、目に入るからだそうです。 光線不足になると、普通は使わない黄色の光も使うようになり、黄色光も吸収されてしまうために、葉は濃い緑色に見えるようになります。反対に光線過多になると、普通は吸収して使う紫外線を、人が日焼けするように、色素を作って逃がそうとするために、葉はこの色素のせいで赤味(赤紫)がかって見えます。もっと光線過多になると、葉緑素が破壊されるため、葉が黄色くなってきますし急激に葉の温度が上りすぎると、葉の組織が破壊されます。(葉焼け) 光線不足になると、普通は使わない黄色の光も使うようになり、黄色光も吸収されてしまうために、葉は濃い緑色に見えるようになります。反対に光線過多になると、普通は吸収して使う紫外線を、人が日焼けするように、色素を作って逃がそうとするために、葉はこの色素のせいで赤味(赤紫)がかって見えます。もっと光線過多になると、葉緑素が破壊されるため、葉が黄色くなってきますし急激に葉の温度が上りすぎると、葉の組織が破壊されます。(葉焼け)
ただし、もともとの健康な葉の色が赤紫などの場合は、色の変化に注意しましょう。
色だけでなく、葉のつやも光線によって変化し、適当な光線があたっている葉は適度のつやを持っていますが、光線不足になると、なるべく光線を反射しないように葉のつやがなくなり、反対に、光線過多の場合は反射を高め、蒸散によって過度の水分が失われるのを抑えるために、葉はロウでも塗ったように、硬くつるつるになります。
一般には強い光線ほど植物の生育に効果があるのですが、限度というものがあり、その程度は種類や個体によってばらつきがあります。同じ個体でも、根の状態などによっても違ってきます。その限度を越すと「日焼け」が現れます「日焼け」の直接の原因は葉温の上昇で、遮光を強めたり通風をよくしたり湿度を高めるなどして防ぐようにします。特に高地性のネペンテスは高温に弱い為、夏場は遮光を強めにする必要があります。葉焼けをしてしまった葉は、焼けた部分が茶色や黒に乾いて見苦しくなりますが、植物にとって葉は大切なエネルギー工場ですから、他の病気を併発しない限りなるべくつけておくようにします。
ネペンテスを栽培していく醍醐味としてはやはり大きく立派な補虫袋を付けさせることでしょう。
ネペンテスの栽培家が次々と新しい種類を求めるのは自生地やベテランの栽培家の立派な補虫袋を付けたネペンテスを見てコレクションを増やしていくはずです。
そのような立派な補虫袋を付けさせる為には温度・湿度・日照なども重要ですが採光や鉢の間隔も重要でしょう。ネペンテスの袋には上位袋と下位袋があり大半の種類が下位袋の方が見応えのある大きな袋を付けます。鉢間隔をつめて置くと上に向かってばかり伸び枝が徒長した先に付ける袋は小ぶりな上位袋になります。鉢と鉢の間隔を十分に開けて、横からの採光と通風に心掛けることにより、がっちりした節間の詰まった丈夫な株に育ちます。
2.温度
 ネペンテスのほとんどの種類が東南アジアの熱帯に分布しているが、その環境は熱帯多雨林帯、高山性多湿多霧地帯、サバンナ気候帯の3つにわけることができる。 ネペンテスのほとんどの種類が東南アジアの熱帯に分布しているが、その環境は熱帯多雨林帯、高山性多湿多霧地帯、サバンナ気候帯の3つにわけることができる。
栽培するには最低でも熱帯多雨林帯に自生する低地性種と高山性多湿多霧地帯に自生する高地性種の二つに分けて栽培する必要があります。
低地性種のネペンテスは種類によって違いはありますが昼間最高で35℃、
夜間 20℃前後で良好に生育するでしょう。したがって、日本では冬季はほとんどの地域で温室などの保温が必要になります。冬季最低 28℃前後に温度を設定すると暖房費もかかるし、異常に温室内の空気が乾燥してしまい、かえって逆効果になりかねますので最低15℃位に設定すれば生育は鈍りますが問題ないでしょう。10℃まで温度が下がっても枯死することはありませんがアンプラリアなどの種類は新芽が萎縮してしまうなどの生育障害になります。鉢内を乾燥気味に育て昼間日照に良く当ててやれば低温にある程度強くなりますが、低温への馴化の幅は小さいようです。夏は温度的には問題なく思えますが、熱帯地方は、晴天日であっても必ずと言って良いほどスコールが降り、気化熱の作用によって一時的とはいえ気温は下がります。その為、温度を下げるための工夫として、遮光ネットを張ったり、風通しを良くするために扇風機を回したりすることが必要になってきます。特に高地性種のネペンテスは自生地が高度の高い所のものほど、現地では温度が下がるので同様の環境を日本で夏に作るには、種類によっては冷房が必要になります。特に問題なのが夜間の温度で、山間部では夜間の冷え込み激しく、昼間の暑さとは対照的になっています。日本の夏は、例年、夜間になっても30℃以上ある熱帯夜が平均25日もあるとなれば、夜間の温度が高温過ぎることになります。昼間最高で20
- 25℃、夜間最低5-15℃前後が理想的な環境でしょう。高地性のネペンテスは夜間の気温が日中よりも5~10℃ 位下がらないと、日中光合成によって作られた糖分が生長のために蓄積されずに呼吸などの代謝で使われてしまので、ストレスを緩和してあげる為にも、夕方に軽く葉水をして蓄わえた糖分を無駄遣いしないようにしてあげることが必要でしょう。これでも十分でなければ冷房に頼らざるをえません。最近では湿度を維持しながら温度を下げるパッド&ファン方式が注目されていますが高地性のネペンテスの栽培には最適でしょう。
3.湿度
 ネペンテスの自生地(熱帯地方)を考えると、同一種類でもジャングルの中の常時湿度90%以上の所に自生していたり、一日に何回かの雨を経験するかと思えば、明るい太陽が照るといった状態で高湿度と低湿度の繰り返しの所もあります。しかしながら日本のように湿度が50% を割ることはほとんどないでしょう。 ネペンテスの自生地(熱帯地方)を考えると、同一種類でもジャングルの中の常時湿度90%以上の所に自生していたり、一日に何回かの雨を経験するかと思えば、明るい太陽が照るといった状態で高湿度と低湿度の繰り返しの所もあります。しかしながら日本のように湿度が50% を割ることはほとんどないでしょう。
栽培においては最低湿度50%以上を目安にしたいものです。
湿度は日照・温度・通気・根の状態などとも関係があり、例えば湿度が高いときは蒸散作用が抑制され葉温が上昇します。特に閉ざされた温室内では野外に比べて通気が悪く急激に温度が上がるので葉やけをしないよう通気を良くする、日照を弱くしてやるなどのバランスをとることが重要です。また強健な根を付けさせていればかなりの乾燥や日差しにも耐えさせることもできます。湿度90%以上で適度な遮光・通気下で栽培すれば確かに大きなみずみずしい袋を付けさせることができますが日本では季節により湿度の変化が大きく常に高湿度に保つには少々やっかいです。高圧ミストや上記のパッド&ファン方式などの設備を付けないとなかなか実現できませんので、環境の変化に適用できるよう湿度だけに頼らずその他の諸条件とのバランスや強健な根を作ってあげることも重要でしょう。
4.通気
植物の新陳代謝、成長を促進し温度を下げて病害を防ぐには通気が重要です。風がないと植物の葉の表面を取り巻く空気は薄い層となり、炭酸ガスが葉の中に取り入れられるのを妨げます。風が吹くとこの層が動き、炭酸ガスが葉に入りやすくなり光合成は活発に行われます。湿度の高いときには特に必要でしょう。
日照が強くて風がないと、葉の蒸散速度が低下し、その結果、葉の温度は高くなり、呼吸は促進され耗が多くなり光合成の能力は低下します。風は植物の葉へ炭酸ガスを供給し、蒸散速度を変え、葉の温度上昇を抑えてくれます。また、微風を送り続けることにより、植物の生育に効果があるだけでなく、細菌の繁殖を防ぎ、病気の予防になります。
ネペンテスは空中湿度を好み、乾いた風を嫌いますので、適当に風から守る工夫も必要です。普通の場合は肌に快い程度の微風が理想的ですが、その程度の風でも水分状態のよくないときは生育を抑制しますので、根の傷んだものや植え替えなどで根を切ったものなどは吸水能力が回復するまでは風に当てないようにします。 また、強い風に当てると葉面からの蒸散が多くなり過ぎ気孔を閉じ光合成は行われなくなります。温室内に扇風機を取り付けて空気の循環をはかり、適当な場所に微風でそよぐ物をぶら下げて、温室内の空気が動いているのを確認できる様にしましょう。
ワーディアンケースなどは小型のファンなどを取り付けるとよいでしょう。
管理
5.潅水
ネペンテスは、種類によって乾燥を好むものや安定した水分を好むものがあり、それぞれの水やりの頻度は異なります。慣れるまでは、水やりは案外難しいものです。水やりの頻度は種類、季節、天候、湿度、鉢のサイズや種類、用土の種類、株の生長速度などによって変わります。目安としてはミズゴケ植えなどの場合、表面が白く乾いたら水を与えます。渇き過ぎの鉢は水をやることで回復しますが、水やりしすぎて根腐れしたものは新しい根が出るまで回復しないために枯れてしまうこともあるので水のやり過ぎには気をつけましょう。ちゃんと水をやっているのに成長点が止まり葉が脱水症状を示してくる時は、水のやりすぎ、または傷んだ用土が原因で、根腐れしている可能性があります。この症状を水不足だと思って、水やりをふやしてしまうので、余計に悪くなることが多いようです。このような時は、株を鉢から抜いて根を調べましょう。健康な根は先が白く、腐った根は先も黒くなっています。根腐れしているようなら、古い用土や腐った根を取り除いて、植え替えます。植え替えたばかりのときは水やりのかわりに湿度を高めてやるのがよいでしょう。ネペンテスが好む水やりの頻度は種類により違います。例えばミラビリスの様に葉が薄く柔らかなものは、より多くの水を要求しビーチ、トランカータなどの様に葉が厚くて革質の厚い葉の場合は、乾燥に耐えます。薄葉のものは乾燥してくると、葉を枯らします。厚葉のものは過湿になると根を枯らして、バランスをとります。
しかし水の与え方は共通しています。ポイントは、鉢底から勢いよく流れ出るほどたっぷりやることと、水はけを良くすることです。水やりには、水分を補う効果のほかに、鉢内に新鮮な空気をとり込む効果や、鉢内にたまった老廃物、鉱物などを洗い流す効果があります。少し湿るくらいに水を与えたのでは、これらの効果は満足に得られません。ネペンテスの根は空気を好み水が少ない時は水を求めて少しでも根を張ろうとするので、いつもびしょびしょに濡れているよりは乾湿の繰り返しのリズムを付けて、空気が通る方が根を健康に保つことが出来ます。種類によってはミラビリスなどのようにびしょびしょに濡れている状態でも元気に生育するものもあります。またネペンテスは湿度は好きですが、株が長時間濡れたままになっていると、病気が出る可能性が高くなりますので、水やりのあとはなるべく早く乾くように通風をよくしましょう。
6.水質
水質はネペンテスにとっては大切です。自生地では雨水などの空気中の水分などのイオン濃度の低い水によって育つので、塩分や鉱物、肥料分をほとんど含まない水を好みます。植物の根は、浸透圧を利用して水分を吸収しているので、鉱物や塩分を多く含む水を与えると、根の内部より外の方が濃度が高くなって、根が水を吸えなくなり、ひどい時は根が傷んでしまいます。特にネペンテスはその適用力が小さく濃度の高い水をやると数日で枯死してしまいます。日本の水道水はEC(電気伝導度)が100μs/cm前後ですからあまり問題にしませんがアメリカ、
オーストラリアなどの大陸では水に溶け込むイオンの量が多くかなり苦労しています。
日本のEC濃度参考( 雨水10~30μs/cm、河川上流50~100μs/cm、河川下流200~400μs/cm )
日本でも沖縄(ECが高い地域)、または井戸水などの地下水を利用されているところでは注意が必要です。
基本的には150μs/cm以下の水を使用するようにしましょう。
水が蒸発する時は純水だけです。また自然界では雨などで流出するイオンも狭い鉢内には蓄積していきます。ネペンテスのように樹上や貧栄養の土地に生育する植物は根からイオンを吸収する量も少なく、植物体の浸透圧も低いため、植物体の根の張り具合にあわせた鉢を選択しないと気が付かないうちに高濃度になっている場合があります。腰水にした時も注意して時々すべての水を交換してあげましょう。
水のPHは植物の根からの養分吸収、又は化学反応と密接な関係があります。植物は養分をイオンの状態で吸収します。PHの度合いでイオン化する物質の量や土に繁殖する微生物の量が変化しますので、出来る限り自生地のPHに合わせるのが無難です。ネペンテスは前述のとうり雨水などの不純物の少ない水を好みます。雨水は二酸化炭素を多く含み弱酸性になっていますので、理想的にはPH6前後の水が良いでしょう。間違っても水がアルカリ性だからといって、薬品(クエン酸、燐酸)などを使用しないようにしましょう。EC値が上がってひどい被害を受けます。
その他、植物栽培で基本的なことですが植物は光の当たる葉などは光合成をして二酸化炭素を多く消費し、光の当たらない根は酸素を消費します。特にネペンテスの根は酸素を好み鉢沿い、用土の表面などに根を広げます。
使用する水にエアーレーションなどをして酸素を混ぜてあげると効果があるでしょう。
水の温度、塩素抜きにも注意します。
7.施肥
ネペンテスは樹上や貧栄養の土地で生活しているので、一般の植物のように土壌から栄養をとったりすることは出来ません。そのために、雨水や空中、そして樹皮の表面などから僅かな養分をとったり、虫を捕らえて消化吸収して育つようにできています。ですから基本的には肥料をあまり必要とはしません。かえって害(肥料焼け)になることの方が多いでしょう。用土がミズゴケなどの有機質の場合は特に用土が腐敗しやすいです。ミズゴケにはもともと微量の養分が含まれているのでネペンテスの栽培にはそれで十分でしょう。ピートモスや赤玉土などの用土を使用すれば施肥してもこれらの持つ団粒構造が養分を吸着し、植物が必要とするだけの養分を離してくれるので、微量の肥料なら与えやすくなります。しかしながら吸着する量にも限界がありますし、植物の生育状態によっても変わってきます。自然界では土壌から養分を吸収できないため虫を捕らえて養分を補うよう進化した植物ですのでその生活リズムを守ってあげる方が長期に健全に育てる近道でしょう。
また、わざわざ与える必要はありませんが餌として昆虫などを袋に入れると肥料に代わる養分として多少の効果があるでしょう。熱帯魚屋に餌として乾燥コオロギ、イナゴなどが売っていますのでそれらを利用するとよいでしょう。
8.病虫害
ネペンテスは比較的病気や害虫に強いものですが、害虫や病気は、弱った株や環境が悪い時に出やすくなりますので、通風などに気を配り良い環境で健全な株を育てることが一番の予防方法です。
少なくとも春と秋には薬剤散布による予防も大切です。(ハダニは紫外線に弱く紫外線の強い夏に子孫を少しでも多く残そうとして以上増殖しますその前に出来るだけ駆除する。またネペンテスは薬品類に弱く30℃以上の高温下では薬害が出ますので、薬剤散布は曇りの日の早朝か夕方にしましょう。希釈倍数は規定の2~3倍位)
ハダニ類などは肉眼では見えず新芽が萎縮したり葉が生気を失い白い小さな斑点などの症状に気が付いた時にはかなり繁殖している状態でしょう。こうなると一度の薬剤散布では駆除できないので一週間置きに2~3回位散布しましょう。一度このような状態になると回復には意外と時間を要します。薬剤散布したからといってすぐには回復しません。また植物の状態をよく観察して調子の悪い原因(生理障害、害虫、病気)を見極めて適切な薬剤を散布することや環境を変えてあげることも大切です。植物は普通硬い細胞膜に覆われており病原体はなかなか進入できませんが害虫の食痕、日焼けあとなどから入り込み複合的に色々な病気を併発することもあり、またその症状も環境、植物の状態などで現れ方が違ってきますので原因の追求は難しくなってきます。そうなる前の防除こそ最大の薬でしょう。
薬剤の種類は様々で厄介そうですが、すべての薬に共通しているのは病原体を殺す薬だけ(強弱はありますが)ということです。そしてネペンテスが掛かるのは害虫は主にハダニ、カイガラムシ、病気はカビなどによって引き起こされる炭そ病、褐色斑点病や
灰色カビ病などで、バクテリアによって引き起こされる軟腐病などはフラスコから出したての苗ぐらいしか見られません。またウイルスによる感染もほとんどないでしょう。従って、ネペンテスが掛かるのは前記の害虫とほとんどカビによって起こされるものでしょう。害虫以外で解らない病徴があれば、
カビによるものと判断すると確立は高いです。近くの園芸店や農協で簡単に手に入る薬を数種類使用する様にします。(病原体がその薬剤に対し抵抗性を持つようになる為、時折変えて用いる)
薬剤処置により病原体を取り除いた後は、生育環境をよくしてあげて植物体が植物自身の力で傷ついた体を治癒するのを待ちます。
もうひとつ最後にネペンテスの根にはセンチュウと言う害虫が寄生します。これが寄生すると駆除する方法がなく、新芽が萎縮し根腐れに似た症状になります。特に弱った株や大きく育って老化した株に見られます。
原因は、植え替えを長期間してなく用土が古くなった鉢を地面に直置きした場合(地面から跳ねたりした泥の中にセンチュウが潜んでいます)が多いでしょう。特に鹿沼土などを使ったミックスコンポスト(混合用土)などを使用した時に発生率が高いようです。予防として植え替えを定期的にし、鉢を棚の上に置くなどして、もしもの時の為、挿し木更新してあげることも必要でしょう。
材料・他
9.鉢
ネペンテスに使用する鉢は、品種、環境、栽培方法、その他諸条件により色々な鉢を使用することが出来ます。鉢の大きさは植物体より少し小さ目ぐらいが良いでしょう。あまり大きな鉢を使うと、用土が乾きにくいばかりか塩類の蓄積にもつながります。
(プラ鉢&ポリポット):透水性はありませんが鉢は安価、軽量で扱いやすく、大量生産には向いています。商業的には大部分がプラ鉢です。
空気を通さないので蒸れやすく、材質が薄い為 周囲の温度変化を受けやすいのが難点です。
(素焼き鉢):色々な種類がありますが透水性があり鉢の表面から水分が気化し、鉢内の温度を下げる効果があります。このような鉢は鉢内が蒸れにくく、根腐れを起こしにくいものです。ネペンテスは通気を好むので好都合ですが、鉢内が非常に乾きやすくうっかりするとからからに干からびてしまいます。また水の中に含まれる塩類などが鉢に蓄積しやすく、長期間の使用は避けた方が良いでしょう。
(駄温鉢):オススメ!!
重たいですが鉢に厚みがあり鉢内の温度がゆっくりしているので根へのダメージも少ないようです。
(ハンギングバスケット):オススメ!! 針金で半円球の枠を作ったものが使いやすいです。 針金で半円球の枠を作ったものが使いやすいです。
用土の流出を防ぐ材料は不織布を使うと、通気にすぐれ、保湿性もあるのでいいでしょう。大きさは直径30センチ以上の物を使用しますが、他の鉢で栽培してある程度の株に仕立ててからハンギングバスケット植えにした方が調子はいいです。
(ヘゴ鉢):ヘゴをくりぬいて作ったもので、見た目、通気もよく優れたものですが、非常に高価であり、植え替えの際にはすべて壊さなければならないし根のダメージも大きいです。
10.用土(コンポスト)
使える用土は、ミズゴケ、ピートモス(成分無調整)、日向土、鹿沼土、赤玉土、バーク、ココナッツファイバー、などたくさんあります。基本としては通気良く、保湿性があり、弱酸性になるようにします。
ネペンテスを初めて栽培される方はまず、最初はミズゴケを使用することをお勧めします。ミズゴケは微量の養分を含み、通気性、保湿性、PHなどネペンテスを栽培する為の条件を数多く備えています。また管理の面でも非常に扱いやすいでしょう。園芸店やホームセンターなどで売られているネペンテスの用土に(ピート+川砂)などのミックスコンポストなどがよく使われています。更には置き肥えまでしてあるものもあります。これらは営利生産上、コストの削減、短期生産などの目的もあり、また生産できる品種も限られてきます。ネペンテスといっても種類がたくさんあり気難しい種類が多いいので、最初は無理に真似てこのような用土またはミックスコンポストにせず、ミズゴケで栽培してその品種の特性を把握してから他の用土または自分なりのミックスコンポストなどを使いましょう。世界各国でも様々な用土が使われ上手く栽培されている方が沢山居ますが試行錯誤の繰り返し、栽培温室の環境、管理を考え確立した結果です。そういった意味でミズゴケ植えが一番失敗が少ないでしょう。
11.植替え
植替えは用土が傷んできたり、植物が元気がなく根腐れの兆候が現れてきた場合にします。
ミズゴケ、ピートなど有機質の用土を使用した場合で1~3年に一度、日向土単用でも最低3~4年に一度は植え替えてやりましょう。植物は根から色々な老廃物、または酸の類を分泌して土壌中の養分をイオン交換によって吸収します。自生地と違い狭い鉢内ではいつのまにかバランスがとれなくなってしまうでしょう。また空気、水の流通も悪くなります。有機質以外の用土を使っているからと言って長期間植替えしないでいると気が付いた時には根がボロボロということにならない様にします。
ネペンテスの根は非常にもろく切れやすいので細心の注意をはらって行います。特に細い根(細根)は水分を吸収する所なのでできるだけ切らないようにします。ミズゴケ植えなどの場合は水の中に漬けて少しずつほぐしていくようにします。どうしても取れない場合は無理に全部取ろうとせず古いミズゴケを残したままその上から新しいミズゴケを足すようにします。植える硬さはやや硬めにしますが水が抜けないようではいけません。鉢底にはガラを入れて通気、水はけをよくします。植えた後はたっぷり水をやり鉢の中に水の通り道を作ってあげます。植え替えするとどうしても根を傷めます。少し日陰の湿度のある所に置いて、水やりを控え(葉水程度)2~3週間程度は傷が癒え新しい根が伸びるのを待ち、根が動き出したら通常の管理をします。植替えの時期は真夏の高温になる時期は避けるようにします。
12.増殖・交配
(挿し木による増殖)
茎が長く徒長した時など枝を切って挿し木することができます。挿し穂を作るには、上から3、4枚の所で切って頂点挿し穂が一本(組織がまだ軟弱なので少し長めに切ります)、その後2節毎位(1節でも良いが1つの芽が腐った時の予備として)に切って何本かの挿し穂を作ります。切る位置は葉のすぐ下がもっとも良いようです、ネペンテスの潜芽は葉の少し上の窪んだところにあるので必ずこの部分をどの挿し穂にもつけるようにします。誤って潜芽のない挿し穂を挿した場合、根は発根しますがいつまでたっても芽が出ません。葉は全体の葉を半分ぐらい落とし水分の蒸散を抑えます。挿し方はいろんな方法があり、切り口を水を張ったビンなどに漬ける方法またはミズゴケ、赤玉土、鹿沼土に直接挿すなどありますが大事なことは水分の供給源である根がないので切り口の水の通り道をつぶさない様、鋭利な刃物で切ります。また雑菌が繁殖して水の通り道をつぶさない様、清潔な器具、用土、水を使いましょう。
ミズゴケやその他の用土に直接挿した場合は潜芽が動くまでの間、越水にしてあげると良いでしょう。
大体1ヶ月~3ヶ月で発根します。時期的には低地性種では温度が20℃あれば夏場の高温期をさければいつでもよいですが生育の鈍る冬場は避けたほうが良いでしょう。逆に高地性種は秋から春にかけて挿すと活着率がいいようです。
そしてもうひとつ重要なのはネペンテスなら枝が徒長したらどの品種でも切っても良いと言う訳ではありません。品種によって(トランカータ、スペクタビリス、ステノフィラなど)は脇芽が出にくい為、成長点を切った為に脇芽が出る前に力尽きて親木が枯死してしまいます。概してこういった品種は挿し穂もつき難く全て失ってしまう羽目になりかねません。これらの品種は徒長しても必ず脇芽が出てから切るようにします。
(取り木による増殖)
舌状削りをしてミズゴケを巻いてするらしいのですが、私自身試したことがないので省略さしてもらいます。
(種子による増殖)
ネペンテスの種子は寿命が短く長くても6ヶ月位で発芽力を失う品種が多く、中には2ヶ月位のものもあります。私は無菌播種をする為、あらゆる所からネペンテスの種子を輸入しましたが9割近くは発芽しませんでした。
運良く新鮮な種子を入手できたら直ぐに播くほうがが発芽率がいいでしょう。微粒の日向土とピート又は粉にした乾燥ミズゴケの混合用土に種子を播き越水をしてサランラップなどをかぶせて湿度を高めにします、1~3ヶ月で発芽します。(半年位の品種もあります)発芽して本葉が数枚になったらサランラップをはずして通常の管理をします。ネペンテスの実生苗は形質がそれぞれ違いますので大きくして自分の気に入った苗を選別する楽しみもあります。
(交配)

雄花 |

雌花 |
ネペンテスは雌雄異株で、またある程度株が老熟してこないと開花しませんし、開花時期にもバラつきがあります。雌花が咲いたら花粉が付けれるように、雄株が咲いたときには花粉を薬包紙などに種名、採取年月日を記入して小分けして冷凍庫に保存しておきましょう。花粉の寿命は定かではありませんが数年は使用できるようです。交配のタイミングは雌花が咲いて何日かするとがく片から多量の蜜が出て異臭を放ちますので、この頃をみはからって花粉を付けます。交配後1日は水をかけないようにします。あとはラベルに交配年月日と交配した種名(♀x♂)を記入します。うまく受精すると4~5ヶ月位で種子ができますので蒴果が割れて種子が飛び散る前に開いて採種しましょう。特に無菌播種をする場合などは蒴果が割れる前に採種することで後の殺菌が楽になります。
|